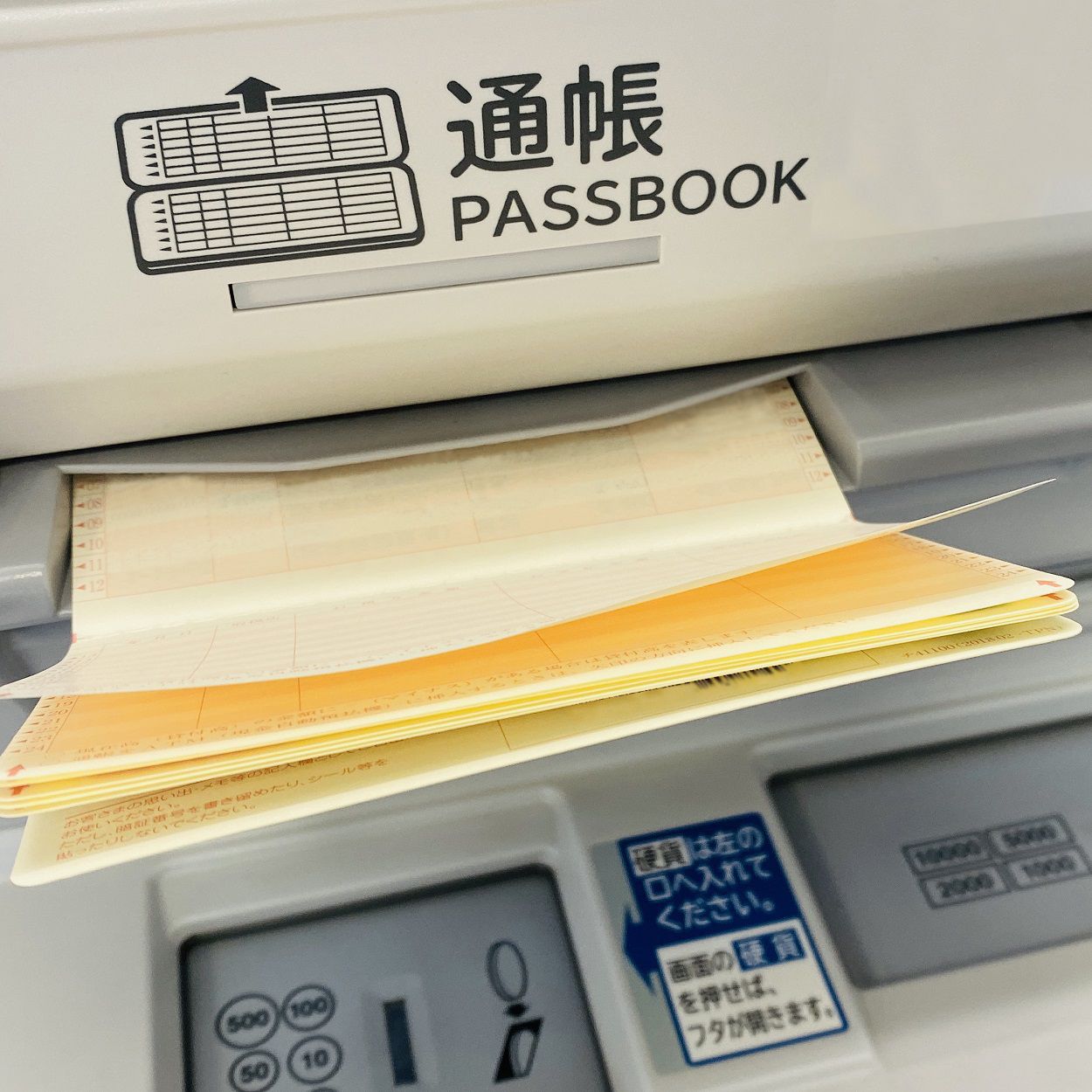パートやアルバイトは時給で働いている人がたくさんいます。月末になるとその月の労働時間×時給でだいたいの稼ぎを計算している人も多いのではないでしょうか。計算した額がすべて銀行に振り込まれればよいのですが、残念ながらそうとは限りません。社会保険や税金などの天引きがあるからです。パート、アルバイトの手取り事情を確認してみましょう。
稼ぎと手取りで差がある人、差がない人
稼ぎと手取りで差があるかどうかは社会保険料と税金を天引きされているかどうかで決まります。では、社会保険料と税金が天引きされるかどうかは、どう決まるのでしょうか?すでに知っている人も多いかもしれませんが、これは稼いだ額で決まります(その金額については後ほど説明します)。配偶者の扶養に入っている人のなかにはパート先の社会保険に入りたくないため、いくら稼ぐかを調整しながらシフトを決めている人もたくさんいます。
一方で、正社員とほとんど変わらないような勤務体系で働いているパート、アルバイトは社会保険料も税金も払って当たり前の環境にあります。当たり前すぎて、いくら引かれているのか、気にしない状態になっていませんか?
稼ぎと手取りでどれくらい差があるのか。社会保険料、税金の額をシミュレーションして確認してみましょう。
年収別、パートの手取りの目安【2023年】
年収130万円から300万円までで、手取り額がどれくらいになるか計算したのが下の表です。
| 年収 | 社会保険料 | 税金 | 手取り額の目安 |
| 130万円 | 194,580 | 21,200 | 108.4万円 |
| 140万円 | 208,764 | 34,100 | 115.7万円 |
| 150万円 | 222,948 | 47,000 | 123.0万円 |
| 160万円 | 237,132 | 59,800 | 130.3万円 |
| 170万円 | 251,316 | 68,200 | 138.0万円 |
| 180万円 | 265,500 | 75,100 | 145.9万円 |
| 190万円 | 283,080 | 82,900 | 153.4万円 |
| 200万円 | 300,660 | 90,800 | 160.8万円 |
| 210万円 | 301,260 | 101,200 | 169.7万円 |
| 220万円 | 318,840 | 109,100 | 177.2万円 |
| 230万円 | 336,420 | 116,900 | 184.6万円 |
| 240万円 | 354,000 | 124,900 | 192.1万円 |
| 250万円 | 354,000 | 124,900 | 201.0万円 |
| 260万円 | 389,160 | 140,500 | 207.0万円 |
| 270万円 | 389,760 | 151,000 | 215.9万円 |
| 280万円 | 424,320 | 156,200 | 221.9万円 |
| 290万円 | 424,920 | 166,700 | 230.8万円 |
| 300万円 | 459,480 | 172,000 | 236.8万円 |
- 健康保険、雇用保険料額は「協会けんぽ・東京都2023年3月分~」を使用。
- 雇用保険料率は「一般の事業」を使用。
- 年齢は介護保険の負担がない40歳未満を設定。
- 住民税は東京都の基準を使用。
- 所得税には復興特別所得税を含む。
- 手取り額は千円未満をすべて切り捨てている。
この年収の範囲内では、年収に対する社会保険料の負担割合はそれほど変わりません。だいたい14%~15%です。
一方で税金には幅があります。年収130万円の税金割合は約1.6%ですが、年収300万円になるとその割合は約5.7%まで上昇します。これは年収130万円から160万円までのケースが例外的に低くなっているためです。所得税は収入が高い人ほど税率が上がる仕組みですが、表にある年収の範囲であれば税率は「課税所得×5%」で一律同じです。
時給1,000円で天引き額を換算。負担が一番重いのは厚生年金保険料
これまで社会保険と税金という言い方をしてきましたが、この記事で社会保険に含むのは厚生年金と健康保険、雇用保険の3つの保険です。税金は所得税と住民税が該当しています。
パートやアルバイトの場合は年収よりも時給に対する割合のほうがイメージしやすいかもしれません。便宜的に年収130万円から300万円の平均値を取ることにします。時給1,000円に対する内訳で負担する額が大きい順に並べると以下の通りです。
- 厚生年金:92円
- 健康保険:50円
- 住民税:32円
- 所得税:14円
- 雇用保険:3円
合計は191円です。このおよそ2割が給与から天引きされます。ですから給与に対する手取りの目安としてはおよそ8割くらいと考えても、大きく外れることはないでしょう。
社会保険、税金を払わずにどこまで稼げる?
稼いだ分をまるまるずべて手取りにしたいなら、社会保険、税金がかからないラインで稼ぎをコントロールする必要があります。
厚生年金、健康保険
月の賃金が88,000円未満であることが条件です。年収に換算すると106万円です。なお、ここでの賃金には臨時の手当て(結婚手当や賞与)、時間外労働、休日労働、深夜労働に対する賃金、通勤手当、家族手当は含まれません。
雇用保険
雇用保険はこの中で唯一、保険への加入に稼いだ額が影響しません。週20時間以上働いていれば加入することになります。稼ぎは関係ありません。そのため、パートのなかには雇用保険だけは加入しているという人もいます。
住民税
年収93万円以下から100万円以下であることが条件です。月額に換算すると77,500円以下から83,333円以下です。住民税は所得割と均等割のふたつの項目があって、所得割は年収100万円以下であればかからないのですが、均等割は住んでいる地域によって年収のラインが93万円以下、96.5万円以下、100万円以下のいずれかになります。そのため人によっては均等割だけを払う、という可能性もあります。均等割の年収基準は自分の住む地域の自治体に確認しましょう。均等割の税額は1年間で5,000円です。
所得税
年収103万円以下であることが条件です。月額に換算すると85,833円以下です。年収には各種手当てや時間外労働、休日労働、深夜労働に対する賃金なども含まれますが、交通費は除くことができます。

鈴木玲(ファイナンシャルプランナー/住宅ローンアドバイザー)
出版社、Webメディアで企画・制作を手掛けたのちに、メディアプランナーとして独立。それまで無関心だった社会保険や税金、資産運用に目覚める。主に若年層に対して社会の仕組みやお金の役割について経験をもとに、わかりやすく伝える。